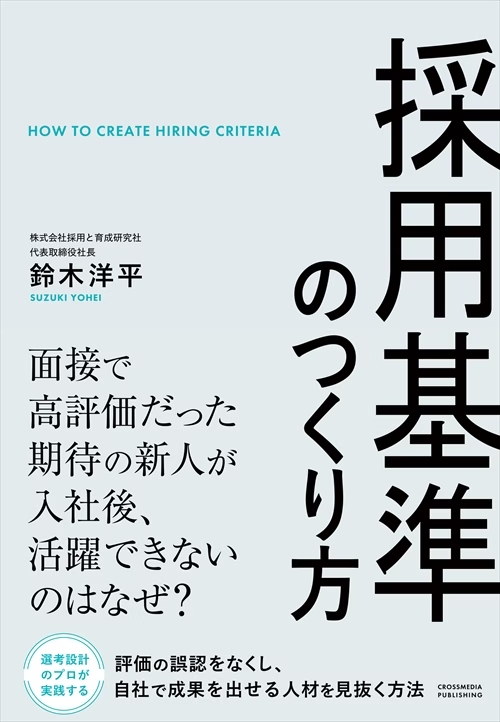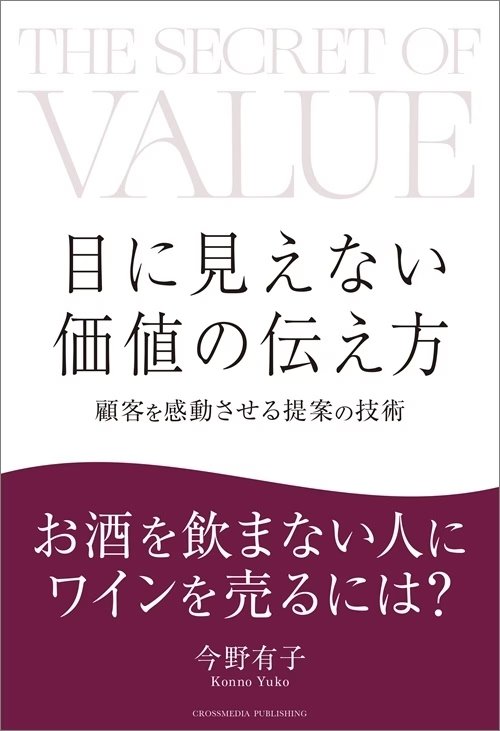面接で高評価だった期待の新人が
入社後、活躍できないのはなぜ?
選考設計のプロが実践する!
「自社で成果を出せる人材」を見抜く方法
「この人なら間違いない」
面接でそう確信したはずの応募者が入社後、期待通りに活躍してくれない。
このような経験に心当たりはありませんか。
期待して採用した人材が入社後にパフォーマンスを発揮できない要因は多岐に渡ります。
真の要因を特定することは難しく、振り返りが行われないため、同じことが繰り返し起こります。
そこで本書では、要因のひとつである「選考での評価が誤っていたかもしれない」という点にフォーカスして、応募者の真の能力を見極め、入社後のパフォーマンスを予見するための採用基準のつくり方と評価手法を解説します。
人材採用に課題を抱える大手企業の人事・採用担当者、中小企業の経営者、面接官を担当する管理職・マネジャーなどにおすすめの一冊です。
【本書のポイント】
・「自社で成果を出せる人材を見抜く」ことに特化した人材採用の本
・評価の誤認を引き起こす3つの落とし穴がわかる
・自社に合ったオリジナルの採用基準を作成することができる
・採用基準を満たす人材を獲得するための選考プロセスを構築できる
・入社後のパフォーマンスを予見するための行動観察手法が学べる