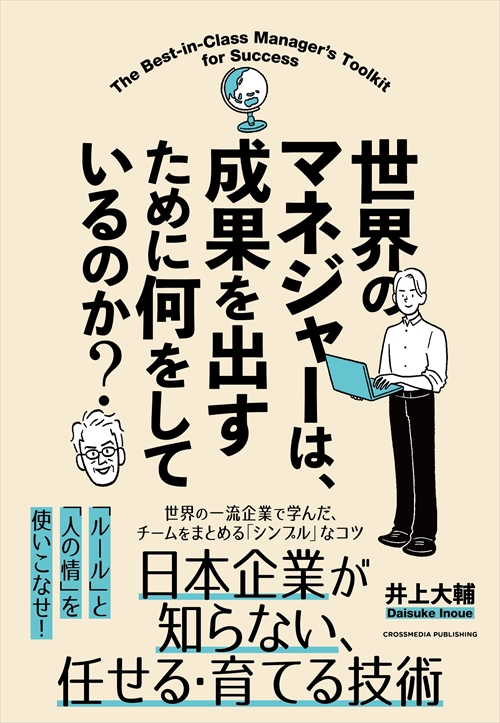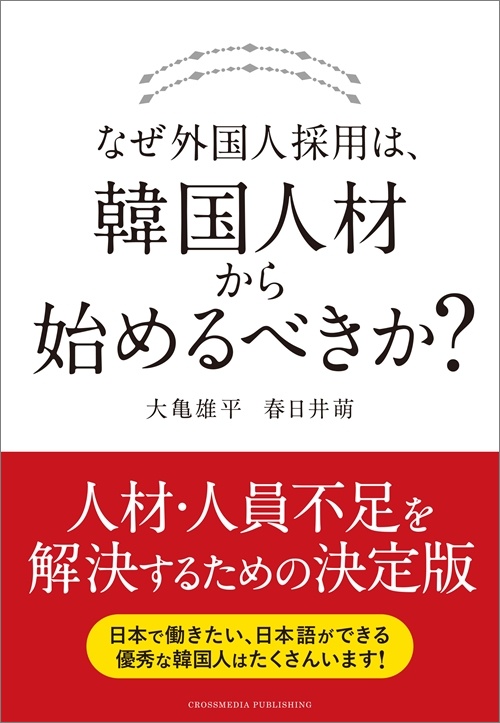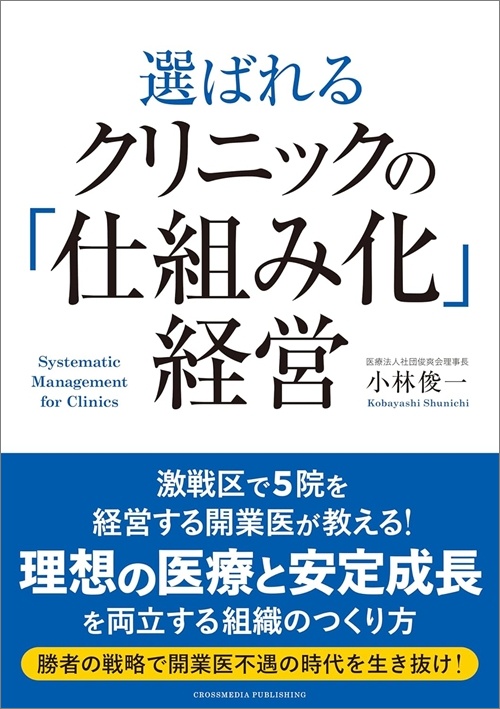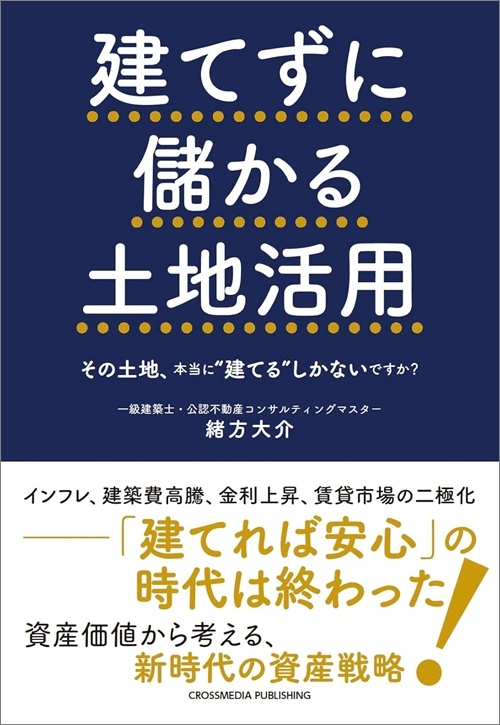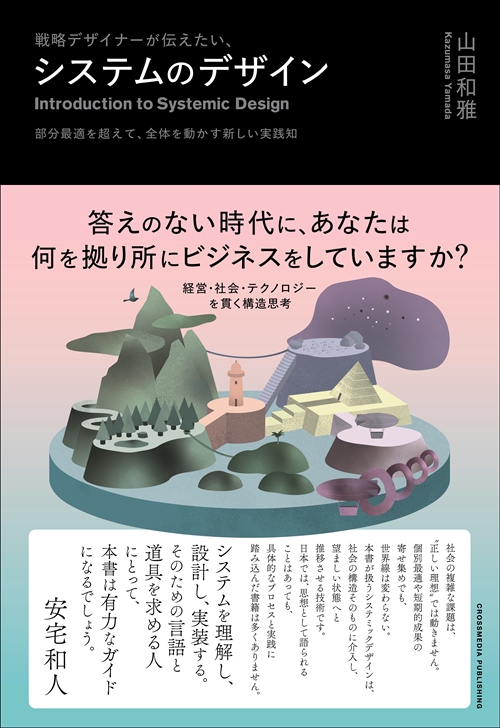◎世界の一流企業で学んだマネジメントのスキル!
◎マネジメントのモヤモヤをストーリー形式で一挙に解決!
◎日常の「1オン1」「MTG」の質が驚くほど変わる!
昭和型のマネジメントはもう通用しなくなり、それでもチームとして成果を出さなければならず、部下のメンタルケアもしなければいけない。マネジメントを学ぶ機会も少なく、自己流でやるか会社のルールに沿っているが、もうどうしていいかわからない、という状態の方も少なくないのではないでしょうか。そんな苦しい時代のマネジャーの羅針盤となるのが本書です。
数々のグローバル企業でマネジャーを歴任してきた著者が、そのマネジメントスキルを体系化。
本書ではマネジメントの有効な手段として以下の5つを解説していきます。
・リレート―関係をつくる
・デリゲート―任せる
・キャリブレート―軌道修正する
・モチベート―背中を押す
・ファシリテート―チームワークをつくる
マネジメントで何をどうすればいいかがはっきりわかる、実用的なストーリーでわかりやすく学べます!
読めばマネジメントの概念が変わる一冊です。
▼ 読者アンケートより
・マネジャーになって1年が経ち、うまくいくこともあれば、そうでないこともあり、日々勉強を重ねてきました。そんな時、この本に出会いました。
物語形式で描かれた主人公の変化や心境が、自分の経験や悩みと重なるところが多く、深く共感しました。どちらかというと人を手段ではなく目的として見てしまう自分の性格に迷いを感じることもありましたが、この本を通じて「間違っていなかった」と救われた気持ちになりました。正直、ビジネス書を読みながら涙があふれるとは思ってもみませんでした。
これからは、本書で学んだスキルを日々意識して、折に触れて見返しながら、チームと共に最大限の成果を出し、より良い組織へと導いていきたいと思います。
心に刺さる素敵な本を書いてくださり、本当にありがとうございました。(30代 会社員男性)