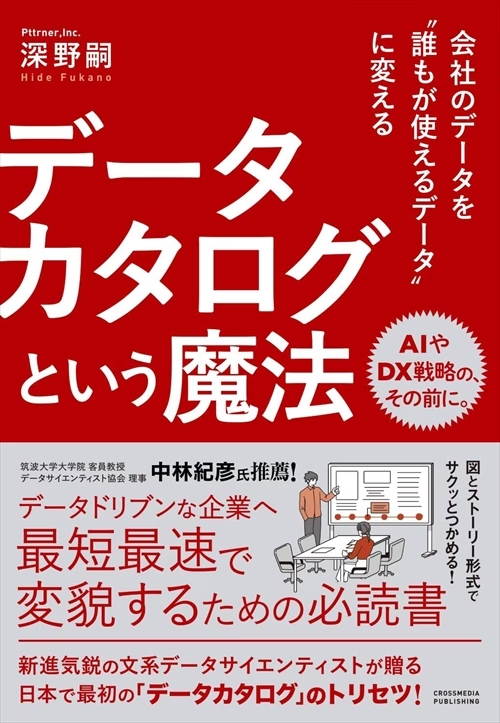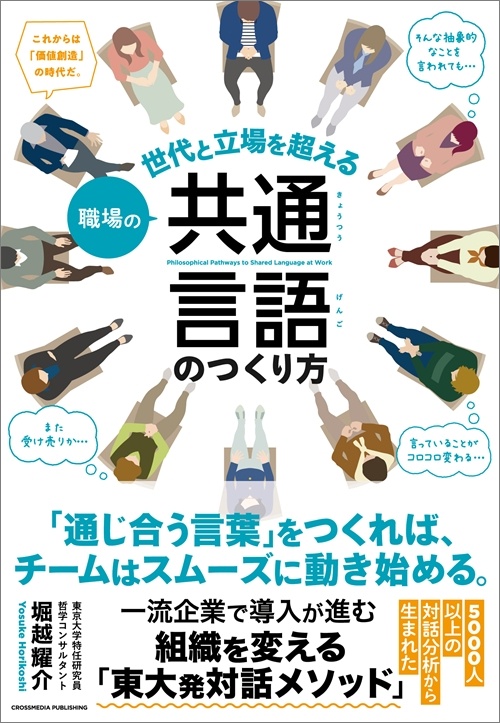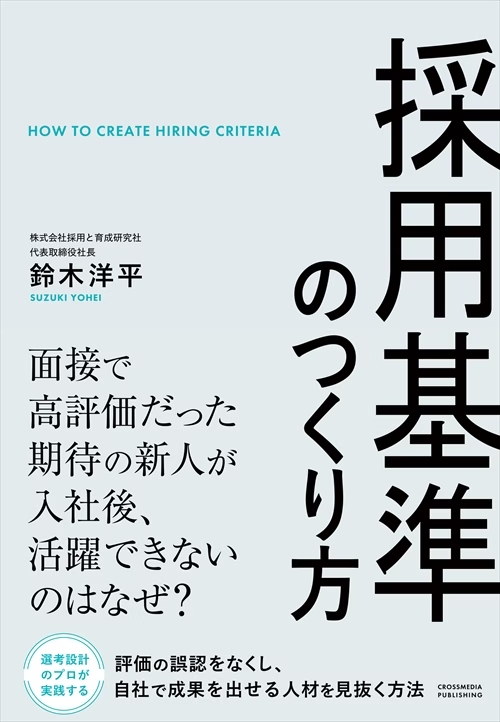5000名以上の対話分析から生まれた「東大発 哲学対話メソッド」
NECソリューションイノベータ株式会社、三井不動産株式会社、株式会社SBI新生銀行、株式会社LegalOn Technologies…一流企業が続々導入!
◎こんな「モヤモヤ」、ありませんか?
・若手に指示しても、期待通りに動いてくれない…
・会議がいつも堂々巡りで、結論が出ない…
・会社の理念やビジョンが、現場に浸透しない…
5000人以上の対話分析を通して見えてきたのは、これらの課題の背景にしばしば「言葉の壁」があること。
同じ言葉を使っていても、意図やニュアンスが微妙にズレている。そんな「通じているつもり」が、組織の成長を妨げているのです。
このような言葉の壁は、世代間ギャップの拡大、働き方の多様化、価値観の多様化から生まれています。
◎その突破口は「共通言語」にあった
本書は、東京大学の特任研究員であり、数々の企業の組織変革を支援してきた哲学コンサルタントの堀越耀介氏が、誰もが腹落ちし、自律的に動けるようになる「共通言語」を構築する対話メソッドを、豊富な事例と共に解き明かす一冊です。
【共通言語とは?】
共通言語は、単なる「合言葉」ではありません。メンバー全員の中で「意味と具体的なイメージが共有され、コミュニケーションと行動の基盤となる言葉」のこと。
たとえば、行動指針に「遊び心」とあっても、その真意を誰も説明できなければ意味がありません。
しかし、「『遊び心』とは、安易な答えに飛びつかず、常にもっとよい方法はないかと工夫し続ける姿勢だ」と全員が語れるようになれば、それは強力な「共通言語」として機能し始めます。
◎「共通言語」が組織を変える
①認識のズレが消え、 意図がスムーズに伝わる!
②世代や立場の壁を越え、 互いの価値観を深く理解し合える!
③遠慮や忖度がなくなり、本質的な議論が生まれる会議になる!
④メンバーが当事者意識を持ち、自ら考え行動するようになる!
⑤全員で「最適解」を共創する文化が育まれる!
マネージャーはもちろん、組織のコミュニケーションに課題を感じるすべての方へ。
今日から現場で使えるフレームワークやテクニックが満載の一冊。