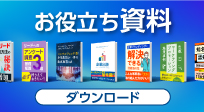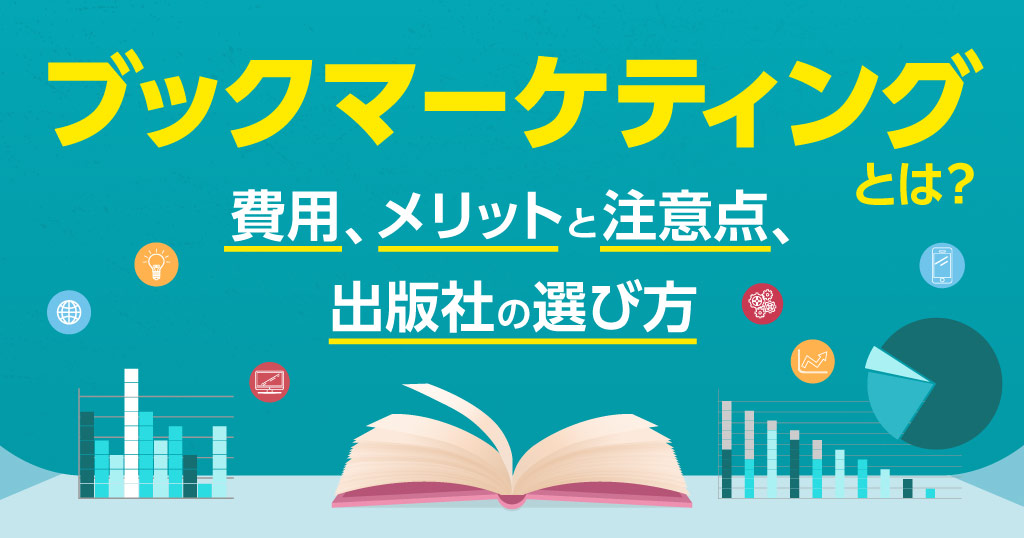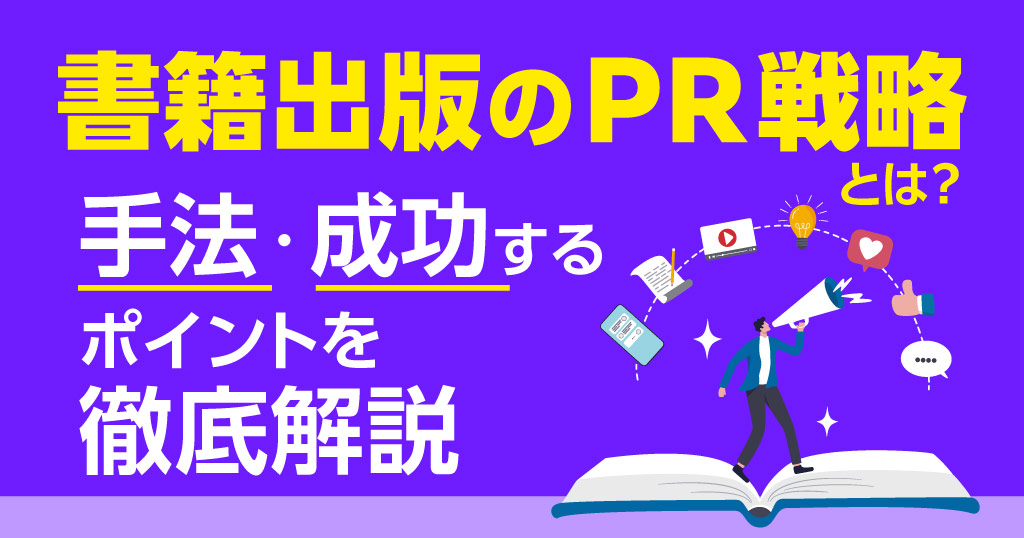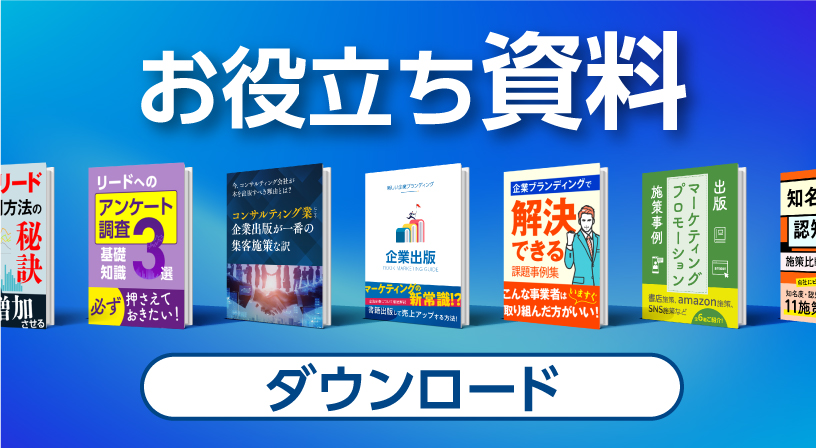- カテゴリ
- タグ

はじめに
生成AIの登場により、web記事による自然検索の在り方が変わりつつあります。今後、web記事にはコンテンツとしての「独自性」と「一次情報性」がより一層求められるでしょう。それは、Googleが重視する品質評価基準EATに新たにE(Experience)が加えられたこととも呼応します。
他人の書籍やweb記事から情報を集め、自身の考察であるかのように仕立てた記事では、今後は集客効果を期待しにくくなるでしょう。これは、AIライティングについても同様のことがいえます。
この記事を読めば、AI時代のweb集客に必要な独自性と一次情報性の重要性、そして効果的なコンテンツの制作方法が分かります。
ウェブサイト集客の最強エンジン、web記事
ウェブサイト集客の主力は、広告に依存しない場合、「企業名(商品名)等の指名検索」からトップページ(商品ページ)への訪問と、「(指名検索以外の)自然検索」から検索ワードに対応するウェブページへの訪問、この二つです。
「(指名検索以外の)自然検索」でウェブページへ訪問してもらうための手段として、来訪者数を稼ぐのが「お役立ち記事」などのweb記事です。アクセス数の多いウェブサイトのランディングページの多くは、GAなどのウェブ解析ツールで確認すると、本文ではなく「お役立ち記事」であることが実際に多いと思います。
「お役立ち記事」は「顧客の知りたいこと」で、ウェブサイトの本文は「企業が言いたいこと」です。前者は後者より情報ニーズが高いのが普通なため、自然な結果と言えます。
生成AIとGoogle検索表示の新方針
これまで、何か知りたいことがあれば、Googleなどの検索エンジンを利用するのが一般的でした。しかし、生成AIの登場により、「〇〇について教えて」と問いかけるだけで、相応の回答が得られるようになりました。そうなると、「検索する意味」を改めて考える必要があります。
こうした状況に対応するように、Googleは検索表示の方針を変更しました。従来のE-A-T(専門性、権威性、信頼性)に加えて、Experience(経験)が重視されるようになったのです(2022年)。これは、作成者自身の体験に基づいた知見や情報、独自に考え出した知識、発見したデータを重視し、検索順位に反映するというものです。

EEATについて詳しい記事はこちら↓
『EEATとは?SEOで重要視される評価基準について解説!』
生成AI時代のweb記事に求められるもの
生成AI時代において、web記事に求められるのは、作成者自身の体験に基づいた知見や情報です。別の言い方をすれば、コンテンツとしての独自性であり、二次情報や三次情報ではなく、一次情報によるコンテンツであることが重要になります。
従来のweb記事制作を振り返ると、自身の体験に基づかない、他の記事や書籍の情報を引用し、自身の知見であるかのように書かれたものが多かったのではないでしょうか。このようなコンテンツは独自性がなく、二次情報・三次情報に過ぎません。したがって、今後はこのようなコンテンツが上位表示される可能性は低くなるでしょう。
生成AIに安易に頼るリスク
生成AIにweb記事の作成を安易に頼ると、「他人の記事や書籍の知見・情報を拝借して、自身の知見や情報であるかのように書いたもの」になりがちです。
生成AIは、世の中やネット上に掲載されている情報を収集し、その中から信頼性の高いものを選んでまとめるため、間違ってはいないものの、最大公約数的な、いわゆる通説的なアウトプットになりがちです。
自分が何かを知りたいと思った時には、世の中から偏りの少ない回答を提供してくれるため、AIは非常に良い働きをしてくれます。しかし逆に、世の中に自身の主張や想いを伝えたいと思った時には、一般的でありきたりな内容になってしまうため、良い働きとはとても言えません。
AIにweb記事を作成させると、最大公約数的な通説になってしまうので、どの記事も似たようなアウトプットになってしまう可能性があります。検索してみると、似たような記事ばかりが表示され、検索する意味がなくなるという事態を招きます。様々な知見・情報から選択できることが検索の価値であり、最大公約数的な通説を知りたい場合は、検索等せず初めから直接生成AIに質問する方が効率的でしょう。
今後は「まずは検索してみて」ではなく、「まずは生成AIに訊いてみて」が最初に行う行動で、それ以上の様々な知見・情報が欲しい人のみが続けて検索する行動に移ると予想されます。生成AIも、「情報を教えてもらう」から「対話、それも音声対話してみる」に進化すると思うので、「まずは生成AIと話してみて」が最初の行動だと言った方が良いでしょう。生成AIの回答に飽き足らなかった人だけが検索するので、検索結果に表示される記事は独自性や個性がないと存在理由がなくなるでしょう。
Googleもそれを理解しているからこそ、品質評価基準を変更したのではないでしょうか。Experienceとは自身の経験・体験に基づいたコンテンツです。「他人の記事や書籍の知見や情報を拝借して、自身の知見・情報であるかのように書いたもの」では十分とは言えません。
たとえ完成度の高い記事に仕上がっていたとしても、Googleの評価基準から外れているため、上位表示されず、結果として集客は期待できないでしょう。

集客効果が期待できるweb記事とは
では、実際に集客効果が期待できるweb記事とはどのようなものでしょうか。それは、Experienceすなわち「自身の体験」に基づいた「独自性」があり、「一次情報」であるコンテンツです。
「独自性」のあるコンテンツとは、自身の体験から生まれた他にないユニークで個性あるコンテンツです。オリジナルなコンテンツと言い換えても良いかもしれません。自身の体験に基づいて語られるため説得力があり、かつ独自の視点や切り口で面白さを持ちます。
「一次情報」であるコンテンツとは、まさに自身の体験に基づいて書かれたコンテンツです。他者の知見・情報を出典を明らかにして使って書いたものが二次情報、出典を明らかにせずに書いたものが三次情報です。今までのweb記事には三次情報が多く、AIライティングによる記事も、使い方に気を付けないと三次情報になりやすい傾向があります。

「三次情報」でなく「一次情報」を評価すると宣言しているGoogleの方針は、今までのweb記事の作成方法に大きな変革を促すものといえます。自身の体験が限られているため他者の知見や情報に依存してきた記事ライターにとっては試練となる一方、自身で様々な体験を積み重ねてきた企業・作者にとっては大きなチャンスとなるでしょう。
集客効果が期待できるweb記事を作成する方法
仮にあなたが「様々な体験をしてきたが、それを記事として仕立て上げるのは大変そうだし、時間的な余裕もない」と感じているとしましょう。確かに読者がスムーズに読んで消化できる記事を作成するには、それなりのスキルが必要です。スキル以外にも労力・時間が必要となります。
そんな時は、誰かに手伝ってもらえば良いのです。あなたの頭の中に詰まっている「独自の体験・知見・情報」を記事という「形」にしてくれる人です。
多くの場合、経験や知見は体系的に整理されていないかもしれません。それを分かりやすく紐解き、読者がスムーズに読み進められるストーリーに仕立て上げる存在は貴重です。時には自身でも気づいていない知見・情報を発見し、ストーリーに効果的に組み込むこともできます。
そのような支援があれば、質の高い記事作成も実現可能です。この種の仕事を日々行っている人々、それが出版社の編集者です。

出版社の編集力とビジネスコンテンツ制作
出版社の編集とは、単なる文章の校正や校閲にとどまりません。より広範な視点でのクリエイティブな判断や、プロジェクト管理能力が求められます。具体的には、以下のようなスキルが挙げられます。
- 読者のニーズや時代の動向を捉えた上で斬新なテーマやトピックを発案する「企画力」
- 著者自身が自覚していない知見や情報の価値を、対話を通して発見する「洞察力」
- コンテンツを読者に分かりやすく魅力的に伝えるために一つのストーリーとして構築する「構築力」
- 著者との意思疎通を図り、原稿の改善提案を行い、関係者との信頼関係を構築しながら出版までをスムーズに進める「プロジェクトマネジメント(PM)力」

特に、ビジネス書の出版社は、ビジネス領域での幅広い知識と経験を持ち、トレンドや市場の動向を理解しています。そのため、ターゲット層に響く質の高いコンテンツを制作できます。また、ビジネス書出版で培った知名度やブランド力を活かし、顧客(作者)のメッセージに信頼性を付与することも可能です。
さらに、専門的な知識をわかりやすく、興味深い形で伝える技術に長けているため、企業の専門情報を魅力的に発信できます。編集プロセスを通じて、内容の正確性や表現の統一性を確保し、質の高いコンテンツを提供します。業界ネットワークも活用し、専門家や著名な執筆者とのコラボレーションによって独自性のあるコンテンツを生み出すこともできます。
書籍をベースに多様なフォーマット・メディアへ展開することも可能で、幅広いニーズに対応できます。ウェブ記事制作もその中の一つです。
編集力について詳しい記事はこちら↓
『経営者の頭の中を言語化する編集力。「出版」を通して事業を研ぎ澄ます』
おわりに
生成AI時代においてweb記事に求められるのは、これまで以上にコンテンツとしての「独自性」と「一次情報性」です。ビジネス書の出版を通して、独自性と一次情報性のある専門的な知見や情報を書籍という形で生み出すことに長けたビジネス書出版社に、web記事の制作を依頼してみてはいかがでしょうか。
ウェブサイトの記事制作だからといって、必ずしもウェブ制作会社やコンテンツマーケティング会社、AIライティング会社に依頼することが最適とは限りません。ビジネス書出版で定評のあるクロスメディア・グループに、ぜひ一度ご相談ください。
FAQ(よくある質問)
A. 生成AIに安易に頼ると最大公約数的な通説になりがちで、独自性がないため上位表示の可能性は低くなります。
A. 一次情報のコンテンツとは、自身の体験に基づいて書かれたコンテンツです。他者の知見を出典明記の上で使用したものが二次情報、出典なしが三次情報です。
A. 独自の体験・知見・情報を記事という形にしてくれる専門家、特に出版社の編集者に依頼することが効果的です。
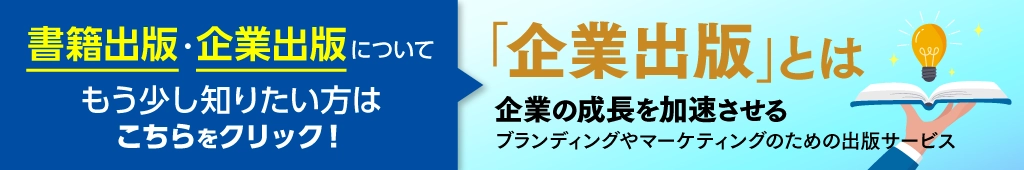
タグ