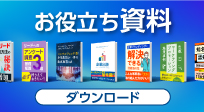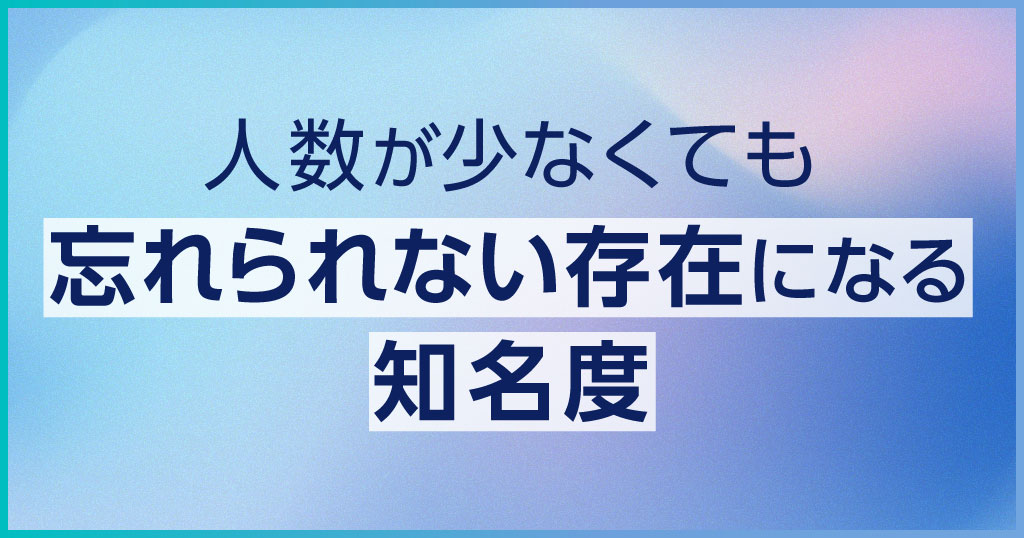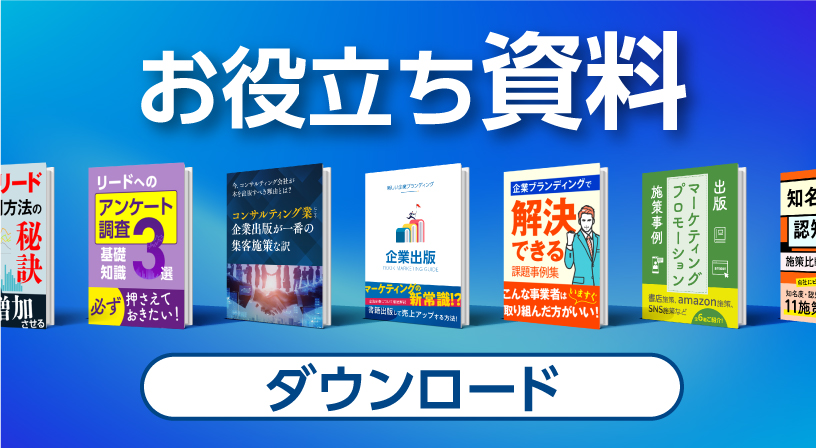- カテゴリ
- タグ

世の中には良い製品、良いサービスが溢れており、ただそれを提供していても、売上を増やし成功するのは難しい時代となりました。そこで注目されているのは、『企業ブランディング』です。
企業ブランディングに興味を持っているがなかなか着手できないとお困りの方、企業ブランディングについて知識を取り入れたい方、本記事では企業ブランディングの基礎知識についてお伝えいたします。
企業ブランディングとは
企業ブランディングの意味
「ブランド」とは、ユーザーが持っている共通のイメージ・実態のない価値のことを指します。そして、「ブランディング」とはユーザーに持ってほしい共通のイメージを持たせたり、実態のない価値を与える方法や施策、取り組みを指します。
ブランディングについて詳しい記事はこちら↓
ブランディングとは?正しい意味や使い方をわかりやすく解説!
そして、「企業ブランディング(コーポレート・ブランディング)」の定義とは、企業そのものの価値を高め、独自の魅力での差別化や自社のポジションを確立することを指します。
企業がステークホルダーに共有したい価値やイメージを高め、社会的イメージが向上するための取り組みが企業ブランディングです。「カメラならこのメーカー」「このレストランなら安心」というように、企業に対してのイメージや価値、信頼などが伝わっている状態を作るのが企業ブランディングです。
受動的に何らかのイメージを持たれるのではなく、企業の浸透させたいイメージを積極的にアピールすることで、企業としてのブランド力を戦略的に高めていきます。
そして、企業ブランディングの最終的な目的は、顧客ロイヤリティの獲得です。すなわち、自社のファンになってもらう事です。
情報社会となった昨今、企業は情報を発信する機会が増え、消費者は幅広い選択肢からの取捨選択が可能になりました。そのため、これまで以上に他社との明確な差別化や自社ならではの魅力の訴求が求められています。また、企業ブランディングは一度取り組めば終わるというものではなく、時代に伴った流行や顧客の変化を汲み取りつつ、リブランディングするなど、時折見直していくことも非常に重要です。
企業ブランディングが必要な企業とは?

「ブランディングが重要とはいうけれど自分の会社には必要ないのではないか。」
そう考える人も多いと思います。ブランディングの要・不要、向き不向きは規模や事業内容で決まるものではありません。強いて言えば、目先の利益や短期的施策にしか、目を向けられない体質の企業にとってはブランディングは不用なものとなります。なぜなら、ブランディングとは中長期的に取り組まねば効果が出ない施策であり、お客様と長く良い関係を築いていきたいと願う企業にとってはブランディングは必須と言えるからです。
そして、「ブランディング」と聞くと、なんとなく大企業が行うことと思っている方が多いのも現状です。しかし、実は中小企業にこそ、ブランディングは必要なのです。
大企業やその他競合との差別化を図るためにも、中小企業こそ、「広告」「価格」「品質」に頼るのではなく、ブランディングを行うことが必要不可欠なのです。
なぜなら、中小企業は大企業がカバーできないニッチなニーズを満たすことができるからです。
有名ブランドや誰もが知っている量販店ではなく、自身の好きなブランドで買う人がいるように、どの分野にもニッチな分野が好きな人は一定数います。大企業もそのような層を認識していてもすべてのユーザーの趣味嗜好をカバーするのは難しく、そのカバーされなかったニッチなニーズを満たすことが中小企業の活路といえます。
さらに詳しい記事はこちら↓
中小企業にこそ必要なブランディングという経営戦略
企業ブランディングで得られる効果

他社との差別化
では、企業と一概にいっても、大手企業、中小企業、零細企業、スタートアップ企業と、いくつかに分類されます。
現在、日本には421万社の企業があり、企業の成長やシェアの確保や拡大にあたって、競合他社との差別化は必須です。その差別化を実現するための施策のひとつが「ブランディング」です。
商品やサービスが豊富にある現代では、多い選択肢の中で、いかに自社を選んでもらうのか、そんなときに必要になってくるのが「差別化戦略」です。
他社との差別化を図るためには、企業文化や理念を念頭に置いて、自社の強みをアピールできるコンセプトを定義することが大切です。
差別化されることで、他社の商品と自社の商品の違いが顧客に認識され、顧客にとってその商品の違いが価値として提供されるのです。
このようにブランドによる差別化戦略とは消費者を主体として、物事を考察しなければならないため、企業目線だけではなく、消費者目線でも差別化ができているか考える必要があります。
差別化のメリット・デメリットについて詳しい記事はこちら↓
差別化戦略を商品や製品・サービスで行うメリットとデメリット
社内での統一感
企業ブランディングが上手くいくと、「自分たちは価値のあるものを提供している」というスタッフのモチベーションにもつながります。職場全体の士気上昇は、結束力の強化、離職率の低下といったプラスの効果を生み出します。
全員が理念に基づいて働くことで仕事のクオリティも上がり、ブランド自体もより強固なものとなります。
組織全体がひとつのゴールを認識して、共通の判断基準を持つことで社員に活力と明確な方向性を与えることができるのです。
自社に合った人材採用
近年、若い人材の数が減少傾向にあることから、優秀な人材の確保が難しくなっています。また、企業と新入社員とのミスマッチから若者の早期離職が増加し、せっかくコストをかけて採用をしても、人材が定着し辛いというのが現状です。
企業の採用活動はネームバリューやブランド力の影響も大きいため、知名度が高くない企業の人材不足は、恒久的な課題といえます。
就職活動や転職活動をするにあたって応募者は企業の理念やビジョン、事業や仕事内容など、注目するポイントは様々です。これらの多くが、企業ブランディングの構成要素に含まれており、企業ブランドが確立されていれば、必然的に人材が集まりやすい企業になります。
企業ブランディングにより、自社が持つ魅力や価値を整理し、採用説明会・インターンシップ・コーポレートサイトなど、求職者との様々なタッチポイントで一貫したコンセプト・情報を発信することで「共感」され、ポジティブな体験につながります。
これにより、企業にとっては「自社に対する共感と理解をもった人材の獲得」につながり、求職者にとっては「自身とマッチした企業への選考」というどちらにもメリットのある採用活動が可能になります。
そのため昨今、「採用ブランディング」に力をいれる企業が増加しています。
採用ブランディングとは、採用において自社をブランド化し、採用したい人材に最終的に就職先として選んでもらえるように意識し、会社の魅力を発信する採用活動のことを指します。採用ブランディングは結果的に企業全体のブランドイメージの向上にもつながる重要な活動なのです。
採用ブランディングについて詳しい記事はこちら↓
採用ブランディングとは?人材獲得に有効な企業出版
顧客のファン化
「顧客のファン化」とは、既存の顧客を、よりエンゲージメント(愛着や思い入れ)の高い顧客に育てることです。
一般的な顧客とファンはリピート購入をしてくれるか否かという点で大きな違いがあります。一般的な顧客は、自社の商品を利用してくれていても、さらに安く、よりスペックの高い商品があれば、そちらに移行する可能性があります。しかし、ファンになってくれた顧客はその商品に愛着を持ち、応援してくれているため、長くその商品を使い続ける可能性が高いと言えるでしょう。
さらにファンとなってくれた顧客は、口コミやSNSで商品やサービスの情報を発信し商品の良い評価を広めてくれる可能性があります。
ひとりのファンから高く評価されることは、多くの新たなファンをつくる可能性を持っているのです。
企業ブランディングによりファンを育てることができ、顧客ロイヤリティの向上が見込めるのです。
企業ブランディング進め方

自社の現状分析
企業ブランディングの進め方として、まず重要なのは自社の置かれている現状や環境の分析をすることです。
そのため、市場調査やデータ分析などのフレームワークを行ったうえで消費者が抱えている潜在的なニーズを汲み取り、商品・サービスを効率的にアピールしていく必要があります。そのためにまずは、自社の強み弱み・競合の市場・顧客のニーズなどをより深く理解するための「環境分析」を行います。代表的な分析方法としては、PEST分析、SWOT分析、3C分析といったフレームワークがあります。
PEST分析
PEST分析とは
- P:Politics(政治的)
- E:Economy(経済的)
- S:Society(社会的)
- T:Technology(技術的)
これら4つの頭文字を取った造語です。PEST分析を使うと、世の中の流れを4つの切り口から分析することができます。外部環境に潜む自社へのプラスやマイナスの影響の要因を整理し、現在または将来にどのような影響を与えるか、把握・予測するためのものなのです。
3C分析
3C分析とは、
- Company(自社)
- Competitor(競合)
- Customer(顧客)
の3つのCから成る分析方法です。自社と競合それぞれの強みと弱みを洗い出し、それらを顧客のニーズに照らし合わせることで、「他社にない自社の強み」を明確にし、現状の課題を解決に導く分析ツールです。
SWOT分析
SWOT分析とは、
- Strength=強み
- Weakness=弱み
- Opportunity=機会
- Threat=脅威
内部環境(強み、弱み)と外部環境(機会、脅威)それぞれに由来する要素を洗い出し、現状を分析していく手法です。自社の可能性や見逃していた強みに気づかせてくれるフレームワークです。
これらのフレームワークを駆使し自社を、環境や他社と比較、分析する事で、自社について様々な角度や視点から見つめ直し理解する事ができるのです。
他にも現状のターゲットやポジショニングを行うためのフレームワークであるSTP分析なども有効です。
STP分析に関して詳しい内容はこちら↓
STP分析とは?マーケティングの基本と具体例を解説!
カスタマージャーニーマップ制作

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを知り、実際に購入・利用するまでを時系列で見える化したものです。カスタマージャー二ーは直訳すると「顧客の旅」になり、顧客が辿る一連の体験を「旅」に例えたものです。
顧客の動きを見える化することで、それぞれがどのようなプロセスを辿るのか、顧客とのタッチポイントはどこかを洗い出すことで、適切な場所・タイミングで適切な情報を伝えることができるようになります。
マップ作成のためのステップは以下の通りです。
- ペルソナの設定⇒自社の顧客として架空の人物像を創出し詳細を設定する
- ゴールの設定⇒問い合わせなのか、購入なのかなど、どこまでをゴールにするか設定する
- フェーズの想定⇒設定したペルソナが実際に自社の製品の認知~導入に至るまでのフェーズ(経路)を細分化していく。
- 導入フローの想定⇒商品を認知し購入に至る導入フローを想定する
- 行動の想定⇒サイトやアンケートなど様々なデータから読み取った行動から、ペルソナの行動を予測する
- 思考・感情の想定⇒ペルソナの思考や感情に関する情報を集めマッピングする
- 求める情報の想定⇒ステップ6までで見えてきたペルソナの抱えている課題などから各行動フェーズ別に異なったペルソナの求める情報が浮かび上がってくる
- 具体的なコンテンツの作成⇒完成したマップから、自社に求められる情報と、発信するべき情報を整理し、そこから必要なコンテンツを作成する。
まずはインナーブランディング
インナーブランディングとは、自社の社員に向けて行うブランディング活動のことです。企業理念やビジョン・バリューなどを社員全体で理解、共感し、社員自ら行動に移せるようになることで自社のブランド価値を高める効果があります。
ブランディングの効果は一般的に企業価値や商品価値を高めるものであり、外部から見える部分にアウターに作用するものと思われがちです。
しかし、「ブランドはインナーから生まれる」と言われるほどインナーブランドは重要です。
ブランディングの初期段階では特にインナーへの効果(社内浸透)を重視するべきと言われているほど、インナーブランディングには注力していく必要があります。
インナーブランディングを行うことで、社員は自社のブランドに沿った行動を自然にとれるようになり、何か突発的な事態が発生した場合でも、スピード感をもってブランドイメージに応じた対応ができるようになります。
インナーブランディングによって企業の価値や魅力を社内に浸透させることで、社員の愛着心が高まり、顧客や取引先に対するブランド価値を高めることにつながります。身内に愛されない企業が競合他社や大手企業以上にユーザーに愛され、評価されることなどあまりないでしょう。
自社や自社の柱となる要素に従業員が愛着を感じられるようになってこそ、他社に負けない魅力的なプロダクトが生まれるのです。
注意しなければならないのは、インナーブランディングの目的は「従業員を豊かにする」ことです。やりがいを感じてもらう事は重要ですが、「やりがい搾取」になってしまわないよう、気をつけなければなりません。企業ブランディングを無理やり社員に背負わせると、動きも鈍く、負担になりかねません。ブランディングと社員の関係性が良ければ、動きも早く、推進力が生まれやすいでしょう。
より効果的な企業ブランディングには、インナーブランディングは欠かせない施策といえます。
インナーブランディングについて詳しい記事はこちら↓
インナーブランディングとは?意味や手法について解説!
次にアウターブランディング
アウターブランディングは、対外的に企業やブランドをアピールしていく活動です。顧客からのイメージはもちろん、収益などをも左右する極めて重要なものです。
アウターブランディングではブランドのコンセプトを定め、そのコンセプトの世界観にあったコーポレートサイトや商品やロゴ、店舗のデザインの制定などを行い、顧客から持たれたいイメージを作り上げる活動です。
消費者がこのタッチポイントとなる様々なものや場面を、ひとつの世界観のもとで総合的にデザインすることで、ブランドとして認知を促します。
アウターブランディングに取り組んでいるのとそうでないのとでは、同じ規模の企業でもネームバリューに大きな差が生じます。アウターブランディングにより、ブランドイメージが定着しているとロゴマークや商品を見て「あの会社だ」と認識されるようになります。
アウターブランディングは、広い意味で「ブランディング」と呼ばれてきた施策です。主に企業ブランディングと商品ブランディングからなり、顧客など外部のステークホルダーに対してブランド情報を発信、定着を目指して活動していくことを指します。
そして、重要なのはインナーとアウター、どちらかを重要視するのではなく、どちらにも同じように力を入れることです。セットで考え取り組むことで、質の高い企業ブランディングとなります。
企業ブランディング成功事例

タニタ
タニタといえば、体重計や血圧計、カロリー計などの健康器具を製造・販売しているメーカーで、「世界の人々の健康づくりに貢献する」というコンセプトを掲げている企業です。
タニタは、社会的意義のあるコンセプトを前面に押し出し、社員の健康を守るために高栄養・低カロリーの食事を提供する「社員食堂」をはじめたことで話題となりました。
この結果、社食向けのレシピ本の販売や一般の人も利用できる「タニタ食堂」を出店するなど企業ブランディングを向上させました。この活動により、自社の事業活動も拡大させることができ、消費者に「タニタのレシピは健康的である」というイメージを抱かせることに成功しました。
Apple
企業ブランディングの成功事例として代表的なのはAppleです。iPhoneやMacなど、Apple製品の利用者は多く、世界中で愛用されています。
Appleの顧客には「Appleの製品だから購入する」という熱烈なファンが多数います。このようなファン層は、Appleのブランディングによって形成されました。
シンプルで洗練された独自のデザインと使いやすい操作性、ユーザーの感性や感情に強く訴求する言葉とデザインの力によってAppleは強いブランド価値を持つ企業へと成長しました。
製品に触れたことがある場合、Apple製品と聞くだけで、機能性やデザイン性、信頼性など、様々な良いイメージをすぐに思い出すことができると共に、どこか「かっこいい」といった印象を持つ人が多いかと思います。
正しい企業ブランディングによってApple社は「Apple」というブランドそのものに価値を生み出す事ができたのです。
まとめ
本記事では、企業ブランディングを行うことで得られる様々なメリットや効果と共に、企業ブランディングの進め方についてご説明してきました。
企業ブランディングが如何にビジネスにおいて重要であるか、ご理解いただけましたでしょうか。商品やサービスが溢れる現代において、企業ブランディングはどんな企業にも求められています。自社のブランド価値となるコンセプトの制定と育成、発信が上手く出来れば、長期的な利益に繋がります。現代社会で戦い抜ける企業になるためには企業ブランディング力は今後ますます必要となるでしょう。

タグ