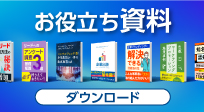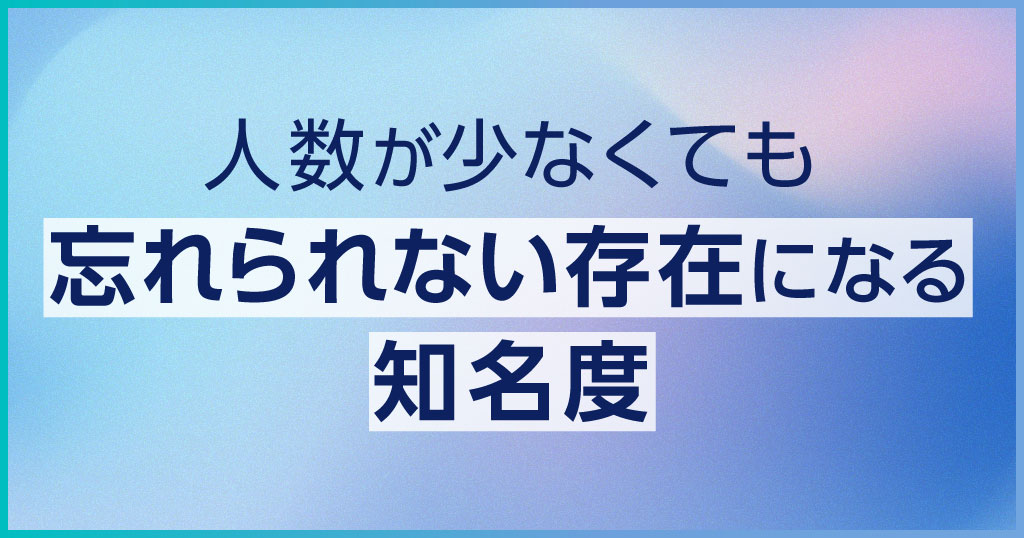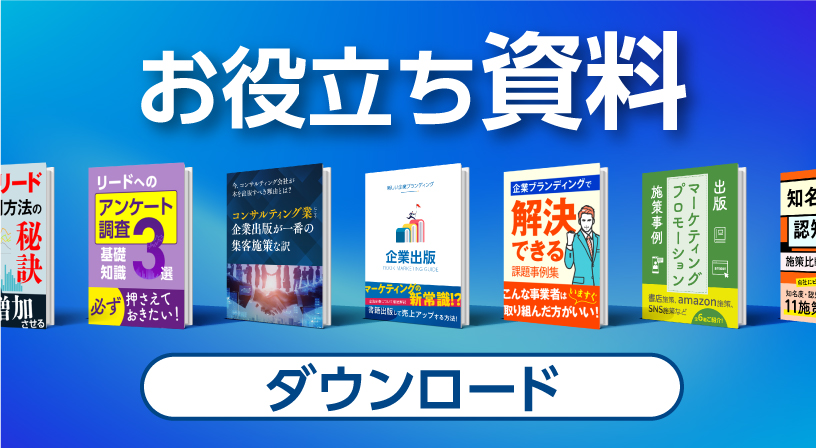- カテゴリ
- タグ
-1.jpg)
「カスタマージャーニー」という言葉をご存知でしょうか?これは、顧客が商品やサービスと出会い、購入に至るまでの過程を可視化したものといわれています。
しかし、正確には「顧客にこう動いて欲しい」というマーケターの願望を可視化したものです。実際の顧客の行動は複雑であり、可視化することは困難なのです。
今、多くの企業がマーケティング戦略の一環として、もしくはCXの計画を立てる上で、カスタマージャーニーを作成し、顧客体験の向上に取り組んでいます。しかし、従来のカスタマージャーニーには大きな欠点がありました。
それは「競合」の存在が考慮されていないことです。顧客は、あなたの会社と出会う前から、そして出会った後も、常に他の選択肢と比較検討しながら購入を決断していきます。
実際に作成されたカスタマージャーニーを見てみると、競合に関して書かれていないことが多いのではないでしょうか。競合がどこにも現れないことが一般的です。
この記事では、競争戦略の視点を取り入れたカスタマージャーニーについて解説します。
顧客が最終的にあなたの商品・サービスを選ぶためには、3つの異なる競争に勝ち抜かなければなりません。それぞれの競争における戦い方を知ることで、より効果的なカスタマージャーニーを設計し、顧客獲得を実現できるはずです。
- カスタマージャーニーの欠点:競合不在の顧客体験
- カスタマージャーニーとエンゲージメントマーケティングの関係
- 選ばれるための3回戦とは:顧客獲得のための競争戦略
- 第1回戦:「そもそも何をするのが最も良いか」の選択:解決策間競争
- 第2回戦:有力候補への生き残り競争(5~10の選択肢⇒3の選択肢)
- 第3回戦:3者による厳しい比較検討競争(3の選択肢⇒1に決定)
- それぞれの戦いの勝ち方
- 第1回戦:「そもそも何をするのが最も良いか」の選択:解決策間競争に勝つためには
- 第2回戦:「有力候補への生き残り競争」に勝つためには
- 第3回戦:詳細な比較検討
- 総括:カスタマージャーニーを2Cバージョンから3Cバージョンにバージョンアップしよう
- おわりに
カスタマージャーニーの欠点:競合不在の顧客体験

従来のカスタマージャーニーは、顧客と自社の関係性に焦点を当て、顧客がどのように商品・サービスを知り、興味を持ち、購入に至るかというプロセスを可視化することを重視してきました。
しかし、現実の顧客行動は大きく異なります。顧客は常に複数の選択肢を比較検討し、その中で最適なものを選び取ろうとします。自社は、顧客から見ると沢山の選択肢の中の一つに過ぎないという当たり前のことを忘れがちなのです。
例えば、車を購入する場面を考えてみましょう。最終的に2〜3車種に絞り込み、販売店と値引き交渉をする段階になるまでには、顧客は多くの車種を検討しているはずです。セダン、ワゴン、SUVなど車種タイプから始まり、価格帯、大きさ、燃費など、さまざまな要素を考慮しながら、徐々に選択肢を絞り込んでいきます。
さらに遡ると、「そもそも車を買うべきなのか?」という根本的な問いから始まるケースもあります。旅行や家のリフォーム、子供の教育資金など、他の選択肢と比較検討する段階が存在するのです。
従来のカスタマージャーニーでは、こうした競合との比較検討視点が欠けていることが多く、顧客の心理や行動を正確に捉えきれていません。言い換えれば、机上の空論になりがちなのです。
カスタマージャーニーとエンゲージメントマーケティングの関係

エンゲージメントマーケティングとは、顧客と長期的な関係を築き、顧客ロイヤリティを高めることを目的としたマーケティング手法です。
顧客との絆を深めることで、継続的な購入や、ファン化した顧客の推奨口コミを通じた新規顧客の獲得といった効果が期待できます。(ここでの「エンゲージメント」は「関係性」や「絆」を意味します)
カスタマージャーニーは、このエンゲージメントマーケティングを顧客視点で全体的に設計したものといえます。
顧客が商品・サービスとどのように出会い、どのような体験を通じて関係を深めていくかを可視化することで、エンゲージメントを高めるための施策を立案することが可能になります。
選ばれるための3回戦とは:顧客獲得のための競争戦略

顧客があなたの商品・サービスを選ぶためには、以下の3つの異なる競争に勝たなければなりません。
第1回戦:「そもそも何をするのが最も良いか」の選択:解決策間競争
この段階では、顧客はまだ具体的な商品・サービスを検討しているわけではなく、「自分の課題を解決するために、どのような方法があるのか?」を模索しています。競合相手は、あなたの会社の直接的なライバル企業ではなく、他の解決策そのものです。
例えば、ダイエットをしたいと考えている人がいるとします。この段階では、顧客は「ジムに通う」「食事制限をする」「ダイエットサプリを飲む」など、さまざまな選択肢を比較検討しています。
この競争に勝つためには、「大局的視野」「専門性」「公正さ」を意識することが重要です。
顧客が幅広い視野で選択しようとしている段階であるため、一方的な売り込みではなく、顧客にとって有益な情報を提供する必要があります。専門家の意見を参考にしたり、客観的なデータを示したりすることで、顧客の信頼を得ることが重要です。
第2回戦:有力候補への生き残り競争(5~10の選択肢⇒3の選択肢)
第1回戦を突破し、顧客が具体的な商品・サービスを検討し始めると、今度は多くの競合との比較検討が始まります。例えば、ダイエットサプリに絞ったとしても、市場にはさまざまなメーカーから多種多様な商品が販売されています。
この段階では、顧客はすべての商品を詳細に比較検討するのではなく(面倒を避けて楽に選びたいという心理が働くためです)、大雑把な、もしくは感覚的な判断基準で選択肢を絞り込んでいきます。この段階を突破できなければ、最終決戦に臨むことはできません。
そのため、「〇〇で選べば自社商品は外せない」といった明確な差別化ポイントを顧客に提示することが重要です。
例えば、「安全性で選ぶならA社のサプリ」「効果の速さで選ぶならB社のサプリ」といった自社の強みが際立つ評価軸、選択基準を提示することが重要です。マーケティング戦略で言うところのポジショニングです。
第3回戦:3者による厳しい比較検討競争(3の選択肢⇒1に決定)
実は、人が真剣に比較検討を行うのは、対象が3つまたは2つの時です。三つ巴の戦いや、両雄の一騎打ちという表現が示すように、この段階で顧客は初めて詳細な比較を行います。
機能、品質、外観、肌触り、使い心地、アフターサービス、価格、世間の評判、さらには見栄を張ることなど、あらゆる要素を考慮し、最終的に「一つ」を選びます。
この競争に勝つためには、顧客の立場に立った競合比較表を作成し、自社商品が最も優れていることを論理的に説明する必要があります。
顧客が比較検討する際に重視するポイントを把握し、そのポイントにおいて自社商品が優れていることを、客観的なデータや根拠に基づいて示すことが重要です。
例えば、ダイエットサプリであれば、「成分」「価格」「顧客満足度」などを比較軸として、競合との違いを明確に示す必要があります。この場合も、客観性・公正さを保ちつつ自社の強みが自然と浮かび上がるように、自社に有利な評価軸・選択基準を上手く設定することがポイントです。
それぞれの戦いの勝ち方

第1回戦:「そもそも何をするのが最も良いか」の選択:解決策間競争に勝つためには
顧客は、まだ具体的な商品やサービスに絞り込んでいるわけではないので、視野を広く持って情報収集をしている段階にあります。ですから、自社の商品やサービスを一方的に売り込むのではなく、顧客が抱える課題全体を俯瞰し、最適な解決策を提示する必要があるのです。いわば、コンサルタントのようなスタンスが求められます。
専門家の意見や客観的なデータなどを活用し、顧客にとって本当に役立つ情報を提供することで、顧客の信頼を獲得していくことが重要になってくるでしょう。
しかし、専門性をアピールするあまり、自社の商品やサービスを露骨に宣伝してしまうと、顧客は不信感を抱いてしまいます。あくまで中立的な立場で、公正な情報を提供する姿勢を貫くことが重要です。顧客が納得できるだけの情報量と質を提供し、自社の商品やサービスが「最適な解決策の一つ」であることを、自然な形で理解してもらうことが、この競争を勝ち抜く鍵となるでしょう。
ただし、この解決策間競争は、必ずしも参加する必要はありません。なにしろここでのライバルは他の解決策一般なのですから。ダイエットサプリ商品であれば、ちゃんとした食事療法をする、毎日適度な運動をする、栄養管理士に相談する、医者の指導を受ける等もライバルなのです。
また、参加するには、多大な費用、労力、そして高度な専門知識が必要となります。資金力や人材力に乏しい中小企業にとっては、この競争に参戦することは大きな負担となる可能性があります。業界No1等のリーダー企業に任せて、自社はむしろ、リソースをここでは使わず、後の競争にリソースを集中する方が賢明な場合もあるでしょう。
参加するか否かは、自社の経営資源や市場環境などを総合的に判断し、戦略的に決定する必要があります。重要なのは、安易に流行りに乗ったり、競合の動向に振り回されたりするのではなく、自社にとって最適な戦略を選択することです。
第2回戦:「有力候補への生き残り競争」に勝つためには
顧客が具体的な商品・サービスを検討し始めるこの段階では、競合ひしめく市場の中で、いかに自社を有力候補として残せるかが勝負の分かれ目となるでしょう。顧客は、面倒な比較検討を避けたいという心理から、大雑把な、あるいは感覚的な判断で選択肢を絞り込んでいきます。
この競争を勝ち抜くには、「〇〇で選べば自社商品は外せない」といった、自社に有利な評価軸・選択基準を顧客に提示することが重要です。顧客が重視するであろうポイントで、自社商品がいかに優れているかをアピールしていく必要があるのです。
例えば、前述のダイエットサプリの例で言えば、「安全性で選ぶならA社のサプリ」「効果の速さで選ぶならB社のサプリ」といった具合に、顧客が「これなら!」と思えるような、分かりやすい強みを打ち出すことが重要になってくるでしょう。具体的な戦略としては、以下の作戦が考えられます。
作戦1:「□□で選べば〇〇(自社商品)は外せない」の□□を戦略的に設定する
これは、顧客が商品を選ぶ際に重視するであろう基準(効用やターゲット層など)を明確化し、その基準において自社商品がNo.1であることをアピールする戦略です。例えば、「成分の安全性で選ぶならA社のサプリ」といったように、顧客が重視するであろうポイントで自社商品が優れていることを訴求していくのです。
そうすることにより沢山のライバルの中から自社を選ぶ理由が鮮明になります。更には比較サイトを作成する作者にとってもこの商品を無視できない存在に仕立て上げるのです。
そのためには自社の強みをどのようなものとして打ち出すとライバルより魅力的に映るか、とことん様々な角度から考えることが重要です。マーケターの実力やセンスが問われる仕事です。
自社の強みを際立たせることが出来る評価軸を見つける、もしくは作ることが重要となります。
作戦2:話題になって存在感を増す
商品が多数存在する市場では、顧客は細かい比較検討をせず、認知度や話題性が高い商品を選びがちです。そのため、積極的に情報発信を行い、自社の存在感を高めることが重要になってきます。例えば、テレビCMやSNSでの広告展開、インフルエンサーとのコラボレーションなどを通じて、顧客の目に触れる機会を増やすことが有効です。
話題性のあるイベントやキャンペーンを実施するのも良いでしょう。重要なのは、顧客の記憶に残るようなインパクトを与えることです。差別化ではなく存在感の大きさで勝負するのです。存在が記憶に強く残っていれば有力候補に残れる可能性は高いのです。
これらの作戦を効果的に組み合わせることで、有力候補としての地位を確立し、最終決戦へと駒を進めることができるはずです。
第3回戦:詳細な比較検討
最終的に2~3社の商品に絞り込まれた段階では、顧客は詳細な比較検討を行います。機能、価格、口コミなど、あらゆる要素を考慮し、最終的な購入を決断します。
この競争に勝つためには、顧客の立場に立った競合比較表を作成し、自社商品が最も優れていることを論理的に説明する必要があります。顧客が比較検討する際に重視するポイントを把握し、そのポイントにおいて自社商品が優れていることを、客観的なデータや根拠に基づいて示すことが重要です。
例えば、スマートフォンを販売する会社であれば、「カメラ性能」「処理速度」「バッテリー持ち」などを比較軸として、競合他社の製品との違いを明確に示す必要があります。

評価は公正かつ客観的である必要がありますが、自社の強みを浮き彫りにするような価値の選び方や打ち出し方が重要です。できるだけ自社の強みがクローズアップされるような価値の表現を考えましょう。
一つの価値(選択基準)で自社の強みを十分浮かび上がらせるのが難しいと判断されたなら、敢えて二つの価値を立てて、一つは自社の強みが尖鋭に強調されるものを打ち立てます。
マーケティングを学んだ方なら耳にしたことがあるかもしれませんが、ポジショニング—どの競争軸を設定することで自社の強みを際立たせ、決定打に持ち込むか—が重要です。これがまさにそのポイントです。

総括:カスタマージャーニーを2Cバージョンから3Cバージョンにバージョンアップしよう
今までの3つの戦いを一表にまとめると以下のようになります。
従来のカスタマージャーニーは、「顧客」と「自社」の2者間の関係に焦点を当てたものでした。しかし、顧客は常に他の選択肢と比較検討しながら購入を決断するため、「競合」の存在を無視することはできません。
競争戦略の視点を取り入れたカスタマージャーニーは、「顧客」「自社」「競合」の3者の関係性を考慮した、いわば「3Cバージョン」のカスタマージャーニーといえます。
3Cバージョンのカスタマージャーニーを作成することで、顧客の心理や行動をより正確に把握し、効果的なマーケティング戦略を実行することが可能になります。
おわりに

この記事では、競争戦略の視点を取り入れたカスタマージャーニーについて解説しました。
顧客獲得のためには、3つの異なる競争に勝ち抜く必要があることを理解し、それぞれの競争における戦い方を明確にすることが重要です。従来のカスタマージャーニーから3Cバージョンへと進化させることで、顧客体験を向上させ、顧客ロイヤリティを高めることができるはずです。
ぜひこの記事を参考に、競争戦略に基づいたカスタマージャーニーを作成し、顧客獲得を実現してください。
これまで作成したカスタマージャーニーに競争戦略の視点が含まれていない場合は、ぜひ次回はその視点を取り入れたものを作成してみてください。
参考書籍はこちら:『戦略から始めるエンゲージメントマーケティング』著者:小川共和
タグ