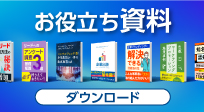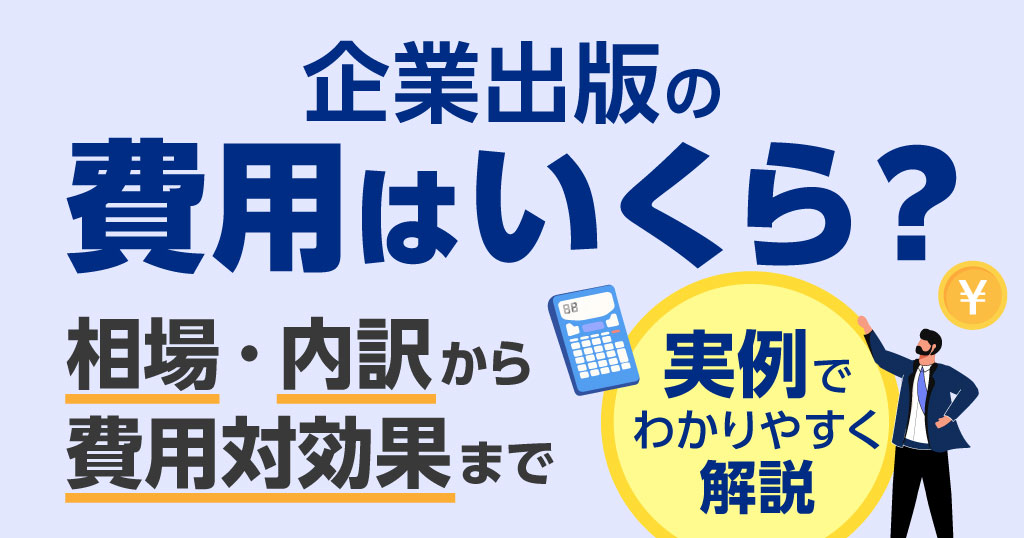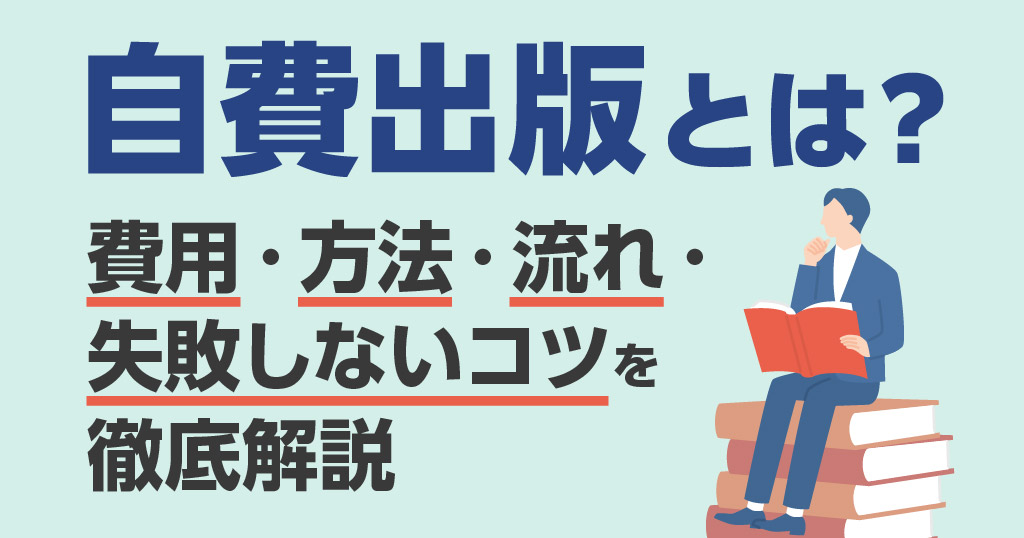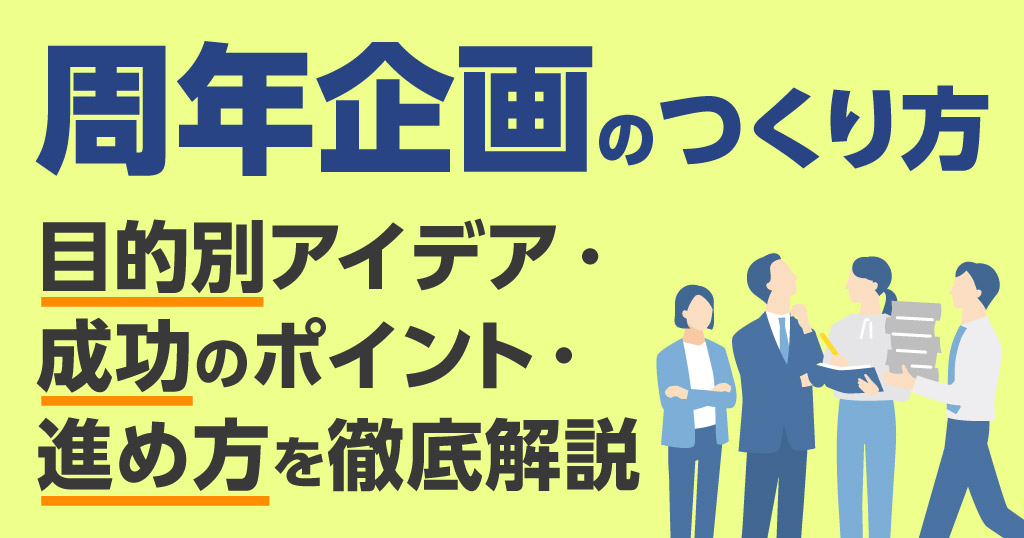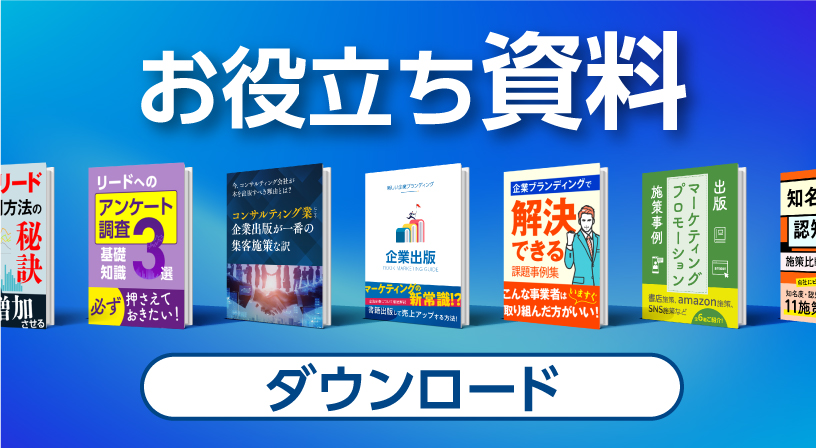- カテゴリ
- タグ
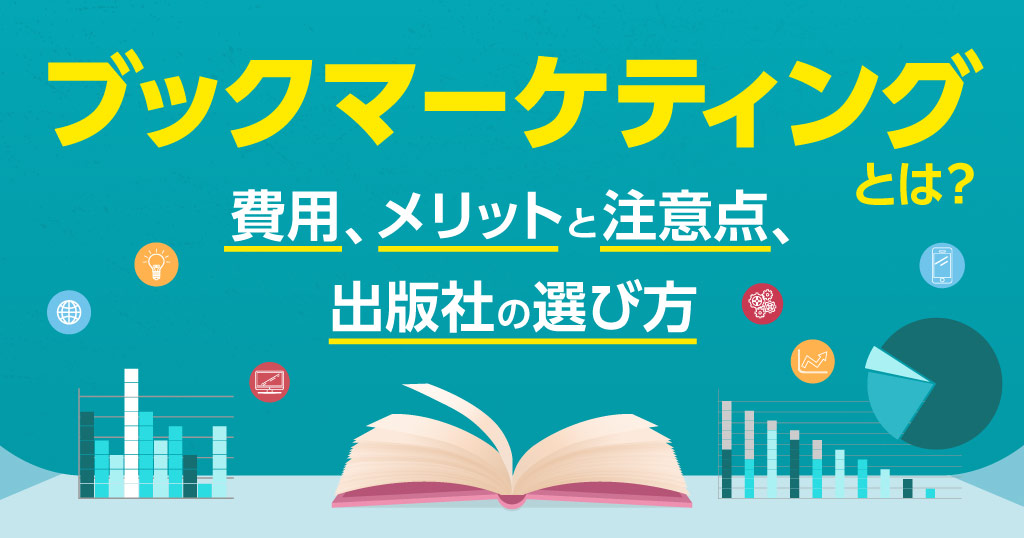
「ブックマーケティング」という言葉を聞いたことがありますか?
SNSや広告では伝えきれない理念や専門性を、書籍という形で体系的に発信することで、信頼性の高いブランド構築や見込み顧客の育成を実現できるのが「ブックマーケティング」です。
本記事では、年間120冊以上の書籍を企画・制作するクロスメディア・マーケティングが、ブックマーケティングの基本から、費用・期間の目安、他の出版形式との違いまでを分かりやすく解説します。これから出版をマーケティングに活かしたい方に向けて、実践的なポイントをお伝えします。
ブックマーケティングとは
ブックマーケティングとは、書籍出版を軸に、企業や個人のブランド価値を高めるマーケティング手法です。
単に「本を出す」ことが目的ではなく、出版を通じて専門性・権威性を証明し、信頼を獲得することで、潜在顧客に対する認知、顕在顧客へのアプローチから見込客の獲得というマーケティングの一連のフェーズを組み立てて、施策を実践していきます。
競合他社との差別化を図るための価格や機能的価値だけでは、見込顧客を獲得できない時代になっています。SNSや広告では伝えきれない社会的な意義や価値を、書籍という信頼性の高いメディアから発信することで、他メディアやイベント、講演などの露出が増え、レピュテーションを高めます。
これらの活動が総合的にマーケティングに効果を発揮し、ブランド向上や人材確保、顧客獲得、投資家からの信頼につながる。これがブックマーケティングなのです。
本記事でいう「ブックマーケティング」は、出版とマーケティングを一体で設計・運用するマーケティング手法を指します。企業出版(カスタム出版、ブランディング出版)は、ブックマーケティングの手段である出版の商品名を指します。
ブックマーケティングのメリットを分かりやすく解説

ブックマーケティングは、単に書籍を出版するだけでなく、企業や個人のブランド価値向上やビジネス成果に直結する効果があります。主なメリットは以下の通りです。
① 信頼性・権威性の獲得
書籍を出版すること自体が、その分野の専門家・第一人者としての立場を確立する強力な手段になります。広告やSNSでは伝えきれない専門性やストーリーを形にすることで、顧客や求職者の信頼を獲得できます。
② 見込み顧客の育成
書籍は一方的な宣伝ではなく、読者に価値ある情報を提供するメディアです。読者が内容に共感すると、自然とブランドへのファン化が進み、長期的な関係構築につながります。
③ 情報の深堀り・教育効果
書籍は文字数や構成に制約が少ないため、SNSや広告では伝えられない深い情報やノウハウを体系的に伝えることができます。社内教育や研修教材としても活用でき、社内外での知識共有や人材育成に役立ちます。
④ SEO・LLMO(AI対策)への効果
書籍を起点としたコンテンツ発信は、Web上での検索流入(SEO)やAI対策(LLMO対応)にも効果があります。
書籍の内容をWeb記事やブログに展開することで、自然検索やAIによる情報整理の精度向上にも貢献します。書籍で整理した一次情報をWeb記事などへ展開することで、自然検索からの流入も伸びやすくなります。
また、著者名・出典・実績を明記したページは、AIが回答を作る際の根拠として採用されやすくなります。
⑤ コンテンツの資産化・再利用
出版した書籍は、セミナー資料、SNS投稿、Webコンテンツ、動画教材など、さまざまな媒体に再利用可能です。出版そのものが独自のブランド資産として活用できます。
ブックマーケティングの施策
ブックマーケティングは、書籍を軸にクロスメディアマーケティングすることで、より高い効果を発揮します。クロスメディアマーケティングとは、顧客に取ってほしい心理変化や行動をシナリオにして、広告などを点ではなく面で展開することです。
以下は各フェーズで効果を発揮する代表的な施策とその特徴です。
| フェーズ | 主な施策 | 特徴・目的 |
| 認知 | プレスリリース | 書籍出版をニュースとしてメディアに発信し、社会的信頼を高める。新聞・Webニュースなどに掲載されることで初速の注目を獲得。 |
| 新聞広告・Web広告 | 書籍の発売を広く告知し、興味喚起を促す。ターゲット層に合わせた媒体選定が鍵。 | |
| Amazon広告 | 関連ジャンルの読者や購買意欲の高い層にリーチ可能。検索連動で費用対効果が高い。 | |
| 情報収集 | 書店展開 | 書店での陳列・特設コーナー展開によって信頼性・露出を強化。リアル接点からのリード獲得に有効。 |
| 書籍紹介サイト | 自社サイトや出版社のドメインでサイトを用意し、書籍の目的や著者プロフィール、活用事例を掲載し、読者との接点を拡大。ダウンロード資料や問い合わせ導線を設けると効果的。 | |
| メディア記事 | 書籍の内容をもとにインタビューや寄稿記事をニュースサイトやビジネスメディアなどに寄稿し、専門家としての認知を強化する。 | |
| セミナー | 書籍の内容をテーマにセミナーを実施することで、潜在顧客と直接接点を持つ。リード育成のきっかけに最適。 | |
| 共有 | Amazonレビュー | 読者の口コミや評価が新たな購入動機を生む。レビュー施策によりロングテールでの販売促進が可能。 |
| 有識者対談 | 業界関係者や専門家との対談を発信することで、書籍の信頼性と話題性を高め、対談相手からの拡散も期待できる。 | |
| 出版記念イベント | 出版を機にオンライン・オフラインでイベントを開催し、既存顧客・新規見込客の関係を強化。 | |
| SNS発信 | 書籍制作の裏話や読者の反応を継続的に発信。ブランドストーリーの共感拡散を狙う。 |
かかる費用や期間の目安

一般的な企業出版の費用レンジ
ブックマーケティングにかかる費用は、書籍の仕様・制作工程・PR施策によって異なりますが、一般的な相場は500万〜1000万円程度です。
主な内訳は次の3つです。
- 制作費(企画構成、取材・執筆、編集、デザインなど)
- 印刷費(ページ数・部数によって変動)
- マーケティング費(書店展開、広告、PRイベントなど)
書籍は一度制作すると長期的に活用できるため、単発の広告やキャンペーンに比べて費用対効果が高いマーケティング資産になります。
制作〜出版までの流れと期間
出版プロジェクトは大きく「企画 → 制作 → 流通・PR」の3段階に分かれます。一般的なスケジュールは以下の通りです。
| フェーズ | 主な内容 | 期間の目安 |
| 企画・設計 | 出版目的・ターゲット設定、構成(もくじ)作成 | 約1〜2か月 |
| 制作・編集 | 取材・執筆・編集・校正・デザイン | 約3〜5か月 |
| 流通・PR | 書店展開、Amazon対応、広告・イベント | 約1〜3か月 |
全体として、7か月〜10か月程度が一般的な出版スケジュールです。また、発売後も販促・PR活動を継続することで、認知拡大やリード獲得などの効果を長期的に得られます。
ブックマーケティングでは、「出版=ゴール」ではなく、「出版=スタート」です。制作段階から目的や活用方法を明確にし、出版後の展開(PR・営業・SNS活用)までを設計することが成功の鍵となります。
出版までの流れについて詳しくはこちら
『書籍が出版されるまでの流れ。6つの制作フロー』
ブックマーケティングのデメリット・注意点
一方で、ブックマーケティングには特有の課題も存在します。事前に理解しておくことが重要です。
① 制作に時間と労力がかかる
企画立案、取材、執筆、編集、校正と工程が多く、通常6か月〜1年程度かかります。短期的な成果だけを期待するとミスマッチになります。
②内容更新が難しい
出版後は書籍の情報を即座に更新できないため、変化の速い業界では内容の陳腐化に注意が必要です。
③読者ターゲットが不明確だと効果が出にくい
誰に向けて発信するかが不明確だと、共感や信頼の構築が難しくなります。企画段階でターゲット設定を慎重に行うことが大切です。
④出版社選びや編集クオリティによって成果が左右される
プロの編集・デザイン・PR体制が整った出版社を選ぶかどうかで、書籍の完成度や拡散力が大きく変わります。単に出版するだけでは十分な効果を得られない場合があります。
ブックマーケティングは「長期的資産」としての価値を持つ一方、企画・制作・ターゲット設計・出版社選びまで戦略的に取り組むことが成功の鍵です。
成功事例
ブックマーケティングは、実際に成果を出した企業の事例から学ぶことが重要です。ここでは代表的な3つの事例をご紹介します。
事例① 税理士事務所の事業拡大(税理士法人ステラ)
長年の実務ノウハウを一冊にまとめて初めて出版した税理士法人ステラは、書籍の発売後に想定を大きく上回る反響を獲得しました。
紙+電子で累計約5,000部を突破し、出版後5か月で経営塾への新規申し込みが多数発生、講座売上は出版前の約1.5倍に。加えて書籍をきっかけに講演や媒体露出が増え、副次的な提携やスポンサーの機会も生まれ、出版費用の3倍のリターンを獲得しました。
[詳しい事例はこちら]
事例② 企業型DCサービスの拡張(株式会社アーリークロス)
企業型DC(企業型確定拠出年金)の導入支援を手掛ける株式会社アーリークロスは、制度の普及やノウハウを含めた書籍を刊行。
その結果、月間の新規導入件数が大幅に増加し、月3件程度から50件にまで拡大。書籍を「名刺代わり」やセミナー配布物として活用することで、見込み顧客の信頼醸成に寄与し、パートナー連携や社内での教育ツールとしても重宝されています。
[詳しい事例はこちら]
事例③ 採用ブランディングの強化(スローガン株式会社)
ベンチャー支援を行うスローガン株式会社は、自社の考えや掲載企業の事例をまとめた書籍を発行。
書籍は学生や採用候補者、企業ステークホルダーへの理解促進に寄与し、採用や企業提携のきっかけになったほか、社内用語や文化の浸透にも役立ちました。社外・社内双方でのブランド強化に貢献しています。
[詳しい事例はこちら]
出版社選びのポイント
ブックマーケティングの成果は、出版社選びに大きく左右されます。選ぶ際のポイントは以下です。
①実績と専門領域
ビジネス書・自己啓発書・専門書など、企業の目的に合った出版分野での実績があるか確認しましょう。
②編集・企画の伴走体制
単なる出版だけでなく、企画立案から原稿作成・編集まで伴走してくれる体制があるかが重要です。
③出版後の販促・PR支援
書籍完成後の販売促進やPR施策までサポートしてくれる出版社を選ぶと、出版効果を最大化できます。
④成果を出す設計ができるか
“出版して終わり”ではなく、集客やブランディングなどの目標に対して戦略的に書籍を活用できる設計があるかを確認しましょう。
出版社の選び方について詳しくはこちら
『出版社の選び方とは?出版社選び方のコツ・基準を教えます!』
まとめ
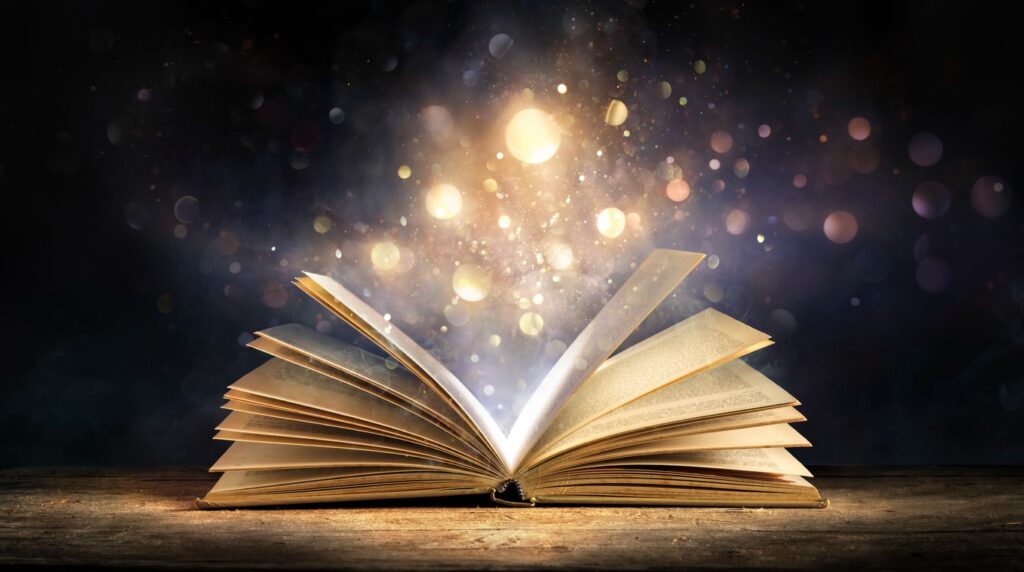
ブックマーケティングは、書籍という長期的資産を通して信頼性・権威性・見込み顧客育成など多くの効果を得られる手法です。
成功の鍵は、ターゲット設定・企画・制作・出版社選び・出版後の活用まで一貫して戦略的に取り組むことにあります。
私たちは企業出版で、ビジネスのお悩みや課題を解決する支援を行っております。
お気軽にご相談・お問い合わせください。
FAQ(よくある質問)
A. 書籍を通じて企業や個人のブランド価値を高め、集客・ブランディング・採用など経営課題の解決を目指すマーケティング手法です。
A. 自費出版は個人向けで自由度が高い一方、発行部数が少なく流通が限定されがちです。企業出版は「課題解決」を目的に、編集・流通・販促まで戦略的に設計しやすいことが特徴です。
A. 実績・専門領域・編集伴走体制・出版後の販促支援・成果設計力の5つの視点で選ぶことが重要です。
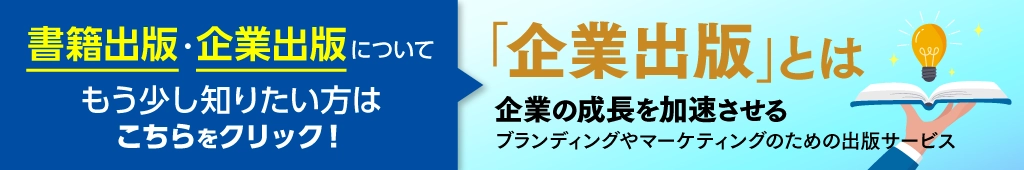
タグ